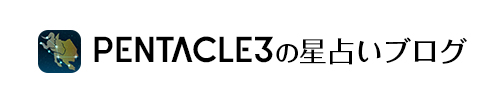こんにちは。
7月7日に天王星が、7年ぶりにサインを変え、牡牛座から双子座へと移動しましたので、天王星のことを書いてみます。
今回は長いので、目次分けしました。
天王星の発見
天王星は、1781年3月13日 にウィリアム・ハーシェル という天文学者によって発見されました。
肉眼で見える太陽系の7番目の惑星として初めて望遠鏡によって発見された惑星ですが、肉眼では見ることは難しいと思います。
過去2022年11月8日に、皆既月食と天王星掩蔽(えんぺい)が同時に起きるという珍しい天文現象が起きまして、日本からも見えるということで、私も東の夜空を長い間眺めていたことがありました。
掩蔽(えんぺい)とは、天体が別の天体の後ろに隠れる現象のことで、月食の輪郭の影の影響で、もしかしたら天王星もちらっと肉眼で見えたりするのかなと思って暫く見ていましたが、見えたのは神秘的な月食だけで、天王星は見えなかったと思います。
天王星の象徴することとして、気象・雷・地震・電気・化学・インターネット・波動・振動などがありますが、影響力としては、突発的な出来事、独自の考え方、理想を追求する、風変わり、独立、或いは孤立した行動、異端、突き抜ける、天才ということに表わされたりします。
西洋占星術では、惑星は人類が発見した時から象徴的意味を持つとされ、土星から先の惑星の象徴することは、その発見時の人の集合的意識、無意識を表すとされています。
つまり、人類がその象徴領域を意識化、体現化できる段階に入ったという考え方で、惑星の発見は人類の意識進化のタイミングと共時的に一致しているという考え方ですが、天体が人の意識を写像しているとも言えるのではないかとも思ったりもします。
ユングの提唱する「共時性」
意識と無意識からなる集合的な心が世の文化をなす神話や現れを通して時空を横断して、自律的に作用するのだとユングは断言する。
無意識、集合的な心は自身を外界に投影し、超越的な意味を発生させる。
言い換えれば、個人の理解を超えた、人生のパターン、秩序、意味があるということである。
それは、宇宙の秩序を認めることによってあらわになるのだが、またそれは、私たちの集合的な投影から作り出されてきたものでもある。「ユングと占星術 」マギー・ハイド著
鏡リュウジ訳
啓蒙思想
天王星が発見された1781年頃は、世界ではさまざまな変革が起こっていました。
18世紀のヨーロッパは、自由・平等・反権威を掲げる「啓蒙思想」の風が吹き荒れていました。
「啓蒙思想」とは人間の理性によって社会をより自由で平等なものに変えようとする思想運動で、人間には考える力があり、それによって真理を見つけ、社会を進歩させようという理念がありました。
その勢いを受けてアメリカでは、1776年に「アメリカ独立宣言」、1789年にはフランスでは「フランス革命」が起こっています。
「啓蒙思想」以前の社会が、神と伝統に従う社会だったのに対し、それ以後は人間自身が主体的存在になって、自由や平等、理性、高次の精神性へと意識が向かう様になっていきました。
それと同時に自然への関心が高まる社会へと進化していきました。
人類は何故だかは知りませんが、進化する様にできていて、理想的だと思える世界やあり方を目指し、追求して進んでいくものだとは思います。(もちろん進化に伴って退化する部分もあるとは思いますが)
でもその力が満ちて限界が来ると、突然変異みたいに、全く予期しない方面から、何らかの可能性に満ちたものの出現が自ずと湧き上がってくるのかもしれません。
それまでの世界も、かつてはより良いもの、理想的なものとして人が築き上げてきたもの(土星)で、価値ある世界だとは思いますが、新しい変革のエネルギー(天王星)がなければ、よりその先の時代に相応しいものは生まれなて来ないということにはなるのかもしれません。
革命や変革という出来事は、壊す、破壊するという意味も含めて、激しく荒々しい事の様に思えたりもしますが、人の進化、人の未来には深く関係していく要素だと思います。
壊さなければ新しいものは生まれないこともあります。
そしてヨーロッパの「啓蒙思想」と並行して、「哲学の進化」の波も起きていました。。
哲学の進化
天王星が発見された1781年、ドイツではイマヌエル・カントという哲学者が、近代哲学史において重要な転換点となる著書「純粋理性批判」を発表しました。
さらにドイツのヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテという作家、哲学者、自然科学者は、そのカントに影響を受けた人物でしたが、後の多くの画家や芸術家、哲学者、生理学者に影響を与えた「色彩論(1810年)」を発表しました。
「自然科学論文集」でゲーテは物理的な地質学、植物学、光学などの実験・観察、研究を重ね、植物の原型(unform)からの変態(metamorphose)を観察して「形態学」を提唱しましたが、それまでの世の進化論を発展させました。
ゲーテの思想の原点は、「人間の内面と自然(宇宙)は響き合っている」というところにありますが、長期の物理的実験、研究を重ねて、独自の見解に至りました。
そういった様々な思想的、哲学的変化の新しい風を受けながら、ヨーロッパでは19世紀にかけては「産業革命」が起こり、人々の生活様式は画期的に変わって行きました。
歴史的に見たら精神の改革、解放の波が、当時の産業革命の様な物理的、経済的な実社会の変化の原動力になっていった様な印象を受けます。
ゲーテについて
ここからは、私のゲーテに対する「天王星」を感じる理由と言える記述になりますが、よろしければおつきあいください。
まず、ゲーテは「色彩論」の中で「色は光と闇の相互作用を、人間が感覚として知覚したもの」と定義していまして、それまでの、ニュートンの色彩光学としての「色は物理的に光のプリズムで分解される」という理論に反論しました。
つまり、何度も実験、観察を繰り返し、結果を加味しながら、色は「心理的・生理的・感情的」現象であり、単なる物理現象ではないという考えに至り、そこに光と闇の介入があることを重要視していました。
色彩の持つ暗い翳り、色彩の持つ高い飽和性は、色彩に厳粛かつ魅力的な表情を与えるものに他ならない。
したがって色彩は(暗さという点で)光が条件づけられたものとみなしうる。
だがそれにしても、色彩は光を欠いてはあり得ない。
光は(闇とならんで)色彩を生み出すもう一つの原因であり、色彩の出現の基礎をなし、ものを輝かせ、色彩を現前させる強い力だからである。「自然と象徴 – 自然科学論集」ゲーテ著
高橋義人編訳 前田富士男訳
光と精神。自然界における光と、人間界における精神は、ともに至高にして細分化し得ないエネルギーである。
「自然と象徴 – 自然科学論集」ゲーテ著
高橋義人編訳 前田富士男訳
ニュートン物理学の考え方が常識だったその時代、ゲーテの色彩論の考えは世間からは受け入れられませんでしたが、現代では、色は「心理的・生理的・感情的」現象だとする「色彩心理学」「知覚心理学」という専門的研究分野もあります。
今の認知科学によると、スコトーマ(心理的盲点)といって、ある情報が目の前にあっても、それを認識できない、あるいは見えていないことに気づかないという状態があるということですが、そもそも、その物質の情報がその人の脳内に、どの程度存在するのかということが見えている状況に影響するということだとしたら、言い方を変えれば、脳内のイメージ、つまりその人の主観による感覚や知覚体験、または感情そのものが、その情報の色を決めているとも言えるかもしれないと思ったりします。
物理的な色彩光学の理論だと、例えば自分が見ている赤と、隣の人が見えている赤は全く同じカラーチャートで示されることになりますが、果たして全く同じなんだろうか?同じ赤でも見る人によっては違いがあるかもしれないということですね。
実際この、ゲーテの色彩論は後の芸術家たちの作品に影響し、その傾向が表れています。
その傾向の詳細については長くなるので、また別枠で記述したいとは思いますが、キャンパスに描く色は、被写体があるとしたら(目に見えないものを可視化しようとしているので、ない場合もある)、実際の色とは違い、そのまま画家の内面にある色が濃く出ていると感じます。
ドローネー、クレー
抽象絵画の先駆者フランスのR.ドローネーも色と光の相互作用を通じて、視覚的エネルギーの表現を追求した人でしたが、ゲーテの影響が見られます。(ドローネーはフランスの色彩理論家のシュブルールの影響が強い)
抽象画、色彩画家、美術評論家のパウル・クレーは、色彩的な表現では、光学的、物理的な色彩理論からは距離を置き、ゲーテの様な光と闇の相互作用による色の創出といった視点を導入しました。
クレーは「色彩は感情であり、音楽・リズム・動き・表現を生む」と考えていました。
絵画において光が発見され、感覚の深みから捉えられたその光は、色彩の有機体(オルガニズム)として、互いに補足し合う価値観や、対になって補充し合う尺度や、同時に幾つかの面における対比から成り立っている。
その様にして偶然身近にあるものを超え、奥行きの効果の最も大きい(我々は星まで見通せる)宇宙的な現実が達成された。
眼は、今や我々の優先的な感覚として、分割並びに統一の同時関係によって特徴付けられる世界の生命力と頭脳との媒介となる。「シュトゥルム」誌よりR.ドローネー
パウル・クレー独訳 土肥美夫訳


シュタイナー、カンディンスキー
神秘学者、哲学者、神智学者、教育学者R.シュタイナーにもゲーテの影響は見られ、ゲーテの自然観・世界観・色彩論を継承しようとした著書として「ゲーテの世界観(1897年)」、「自然科学論集(1897年)」、「ゲーテ的認識の方法(1886年)」、「色彩論におけるゲーテの理論」などを記しました。
霊性を否定する近代の自然科学では生命の本当の姿を捉えることはできないと考えるシュタイナーは、自然(物質)と霊(精神)の間の関係性を示すゲーテの世界観に可能性を感じて、「自然は霊的世界の表現」(一言で言うと)として、ゲーテの理論を発展させていきます。
ゲーテは、自然と精神を根本的に分離したものとは見ていません。
彼は世界の中に偉大な全体、存在の統一的展開を見ようとしていたのです。「シュタイナー芸術と美学」R.シュタイナー著 西川隆範訳
シュタイナーは先立つ講演で、「我々が色彩の背後を見るとき、そこに見出すものは何か。精神(geist ガイスト)だ。色彩は氷と水の関わりの様に精神に関係する。音もまた同様である。」と述べている。
神智学では、精神に係るその様な色彩は、肉眼で捉える自然とは別に「アウラ(aura)」と呼ばれる。「抽象絵画の誕生」土肥美夫著
抽象画家、美術理論家のW.カンディンスキーは、シュタイナーの理論に共鳴するところがあり、交流がありましたが、1911年には「抽象芸術論―芸術における精神的なもの」を発表し、「真の芸術は、物質世界ではなく内的世界に根ざすべきだ」と主張し、色彩における「霊的進化」の道筋を記しています。
ドローネーや、クレー、シュタイナー、カンディンスキーの時代は、天王星発見から65年くらい後になる海王星の発見から、さらに先の時代になるのかなと思いますが、海王星が発見された時代は「人の内面の持つ、より深く掘り下げた潜在意識の世界」をそのまま可視化、具現化しようとする試みが多く表れてきている時代だと思います。
ゲーテは、詩や文学作品においても、それまでの型にハマった形式的な美や思想に対してそれをうち壊す様な、人が主軸になる感情的な型破りな表現をすることもあり、タブーとされる題材を作品にしたりもしました。
当時の、周囲の常識的感覚の世界からは、ある意味突き抜けている「異端児」的存在だったんじゃないかと思います。
そして、ゲーテは自然科学と哲学と芸術を融合して、後々の世界まで影響を与えることになった天才なんじゃないかと思いますが、geist(霊性)とmaterie(物質)は、同じ場所にあるのではないかと私には思えます。
霊性とは、私たち人間全てが持っている魂で、現代の人は「目に見えるものが全て」としてそれを否定する人もいると思いますし、存在を認めても、別次元のものと捉える人もいるとは思いますが、過去の先人たちは、様々な物理的、科学的実験を通して、宇宙の普遍的なものを証明しようとしたのだと思います。
トランジットの天王星
最後に自分の天王星の体験ですが、天王星が逆行を経て自分の太陽牡牛座に入ったのは2019年3月でした。
その頃は自分はといえば西洋占星術のことはまだ知らず、「生活が苦しいなぁ」などと、うすらぼんやり感じてはいたのですが、「なんとかなるだろう」くらいに捉えていて、このまま働いて平凡に人生終えていくものだと思っていました。
でも、突然の配偶者の死で、何かエッジの鋭いスケボーの先かなんかでガツンっと殴られた様なショックに見舞われました。
その後しばらくは様々な出来事もあり、さらにしんどいなということが続きました。
でも、今、双子座へ去って行った天王星を思いながら、以前よりは進化した本来の姿に近くなった様な自分を感じています。
「このまま平凡に。。」とか、「なんとなく、こんなもんかな。。」とか、心のどこかで自覚して感じていることがあったとしたなら、それは天王星が、「本当にそのままでいいの?」と、その人の無意識に、ちゃぶ台返しのサインを投げかけているということがあるかもしれません。
特にトランジット天王星がネイタル太陽サインの頭上に来た時はあると思います。
今は太陽星座が双子座の人ですね。
表面上折り合いをつけているつもりのことでも、実は心の底の無自覚な意志は本人の意識とは全く別の方向へ向いている。
という様なことに気づかせてくれる星。
それが天王星ということなのかもしれません。
ここまで、長い文章にお付き合いくださりありがとうございます。